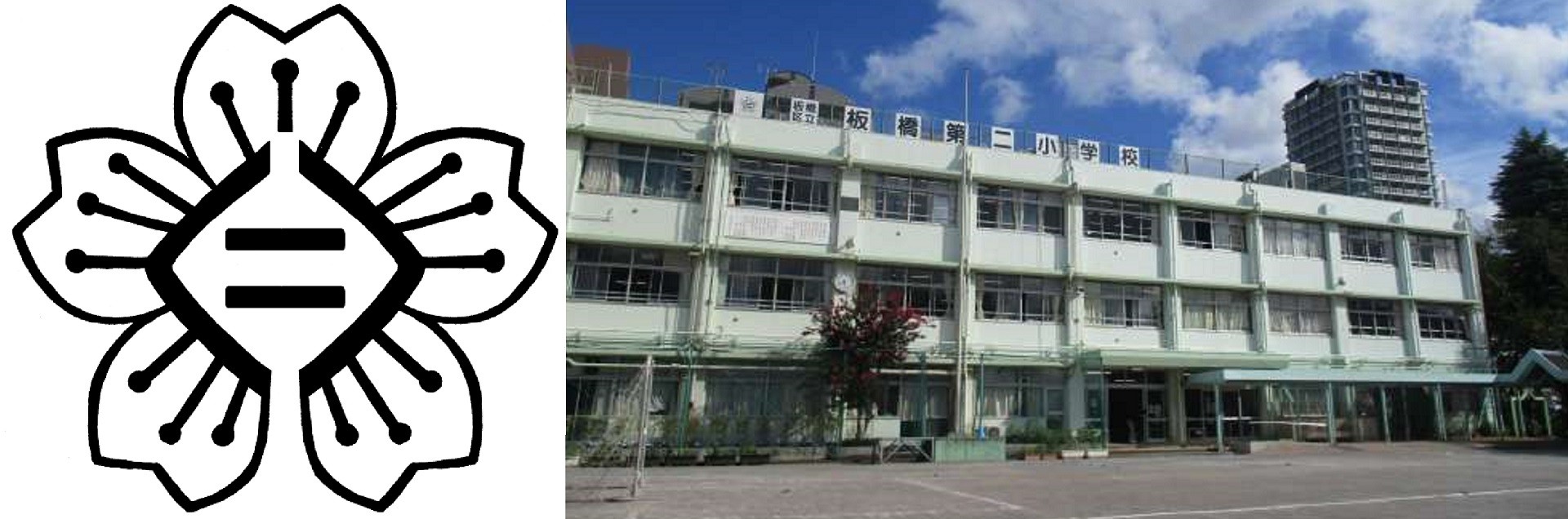★「欠席・遅刻・早退届」は、こちらをクリックして表示されるGoogleフォームから送信してください。(ブラウザはGoogle Chromeをご使用ください。その他のブラウザではGoogleフォームを開くことができないことがあります。)
★出席届はこちらからダウンロードできます。
★給食停止届・給食停止期間変更届はこちらからダウンロードできます。
学びのエリア
板橋区の小中一貫教育では、全区立小学校・中学校において9年間を通した指導計画「板橋のi(あい)カリキュラム」に基づいた教育を行います。
「学びのエリア」では、エリアごとに小中学校で話し合って、エリアの特色を踏まえた「めざす子ども像」と、それを実現するための教育の「基本方針」を設定・共有します。
そして、その方針に基づいて「学びのエリア」で一体となって、9年間を通した教育・取組を行っていきます。
板橋第二小学校は板橋二小・板橋六小・板橋七小が学びのエリアとなっています。
取り組みについての概要はこちらをご覧ください。
板一中 小中一貫学びのエリア 各校のリンク
新着記事
-
板二小では、読書旬間の取り組みとして、図書委員や保護者の方、教員による読み聞かせを行っています。 今日は、朝の時間に担任が交代して、それぞれ別のクラスで読み聞かせを行いました。先生たちの話す声に合わ...
2025/07/09
できごと
-
・牛乳・ごはん・山形県最上町産トマトの西湖豆腐・華風あえ今日は、「とれたて村給食の日」でした。山形県最上町からつやつやしてとても美味しそうなトマトが届きました。「西湖豆腐だけおかわり!」という子どもた...
2025/07/09
給食献立
-
今日の朝はスタディアップタイムでした。1年生は、「絵日記の書き方」を学習しました。平仮名が書けるようになり、できごとや気持ちなどを、文にする練習をしています。2年生は、国語で見出しについて学んだことを...
2025/07/08
できごと
-
・牛乳・ナチョスドッグ・キャベツのクリーム煮・バレンシアオレンジナチョスドッグは、具にスパイシーミートとチーズがはいっています。暑い日にぴったりの味になっていました。
2025/07/08
給食献立
-
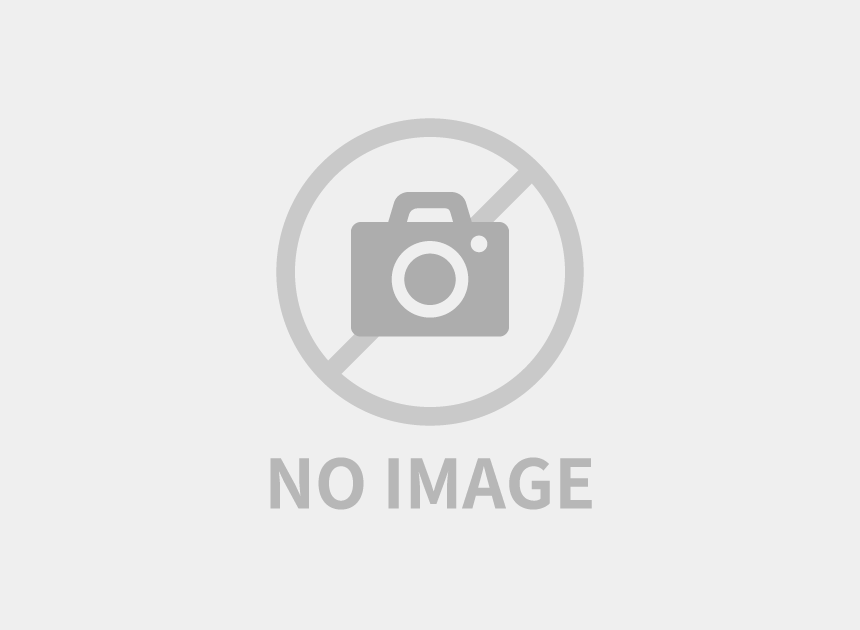
今日は児童朝会がありました。副校長先生から七夕にちなんで、星や宇宙についての話がありました。「織り姫(ベガ)と彦星(アルタイル)は、七夕伝説では年1回会うことができます。しかし星として考えると、遠く離...
2025/07/07
できごと
新着配布文書
-
R7 学校要覧 PDF
- 公開日
- 2025/07/02
- 更新日
- 2025/07/02
-
R7 図書だより7月 PDF
- 公開日
- 2025/07/01
- 更新日
- 2025/07/01
-
R7 学校便り 7月 1ページ目 PDF
- 公開日
- 2025/06/30
- 更新日
- 2025/06/30
-
- 公開日
- 2025/06/30
- 更新日
- 2025/06/30
-
R7 学校便り 7月 4ページ目 PDF
- 公開日
- 2025/06/30
- 更新日
- 2025/06/30