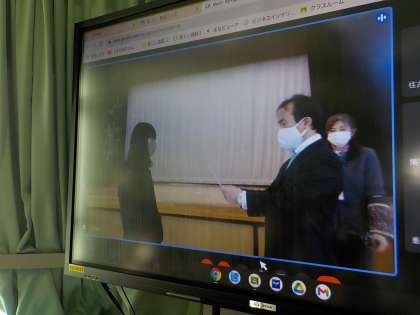1年生の様子
1年生の図工の様子です。「こころのはなをさかせよう」という題材で、卒業していく6年生と新しく入学する1年生に「おめでとう」の気持ちを込めて世界に一つだけの花を考えて描くという活動をしました。6年生に感謝したいことを聞くと、「登校班で安全を守ってくれている」「転んだときに助けてくれた」「板二オリンピックで応援してくれた」などの声が上がりました。皆心を込めてそれぞれの心の花を描いています。
【1年生】 2022-02-10 17:09 up!
児童朝会
本日の児童朝会の様子です。5年生が体育館に整列し、校長先生の「我慢する力」についてのお話を聞きました。「めんどうくさい」という気持ちや、日常の中の誘惑についつい負けてしまいそうになることもありますが、そこをぐっと我慢してやるべきことを進めることによって、結果様々な成長に繋がるというお話でした。最後は日本生態系協会から本校が受賞した「園庭・ビオトープ奨励賞」の賞状を、環境委員会が代表して受け取りました。
【できごと】 2022-02-10 17:09 up!
2月8日
かけほうとううどん 牛乳 うずら卵フライ フルーツヨーグルト
ほうとうは小麦粉を練って太めに切って作った麺を野菜たっぷりの材料と一緒に味噌仕立ての汁で煮込んだ山梨県の郷土料理です。ほうとうには必ずかぼちゃが入っているのが特徴です。麺、野菜と汁を一緒に煮込んで熱々で食べます。武田信玄という山梨県の戦国時代の有名な武将が自分の刀でほうとうに入れる野菜を切ったことから、宝刀と名付けられたと言われています。山梨県は山地で、水田が少なく米の収穫が出来なかったため、麦で作るほうとうがよく食べられていました。昔はほうとうの麺を打てないと一人前の大人ではないと言われ嫁入り修行の第一歩であったようです。家で作った手作りのみそを使い畑で育てた野菜を使って作ったほうとうは家庭ごとの味があるそうです。
【給食献立】 2022-02-08 13:04 up!
2月7日
えびのクリームライス 牛乳 イタリアンサラダ
えびは日本では昔からお正月や結婚式等、お祝い事の料理に欠かせない縁起の良い食べ物です。それは長いひげと腰の曲がった姿が長生きをするお年寄りに似ているからです。また目玉が飛び出していることから目出たしとされ、さらに威勢がよいので縁起が良いとされています。給食で使っているえびは東南アジアにあるマレーシアの海で獲れた天然のえびです。日本では収穫量がとても少ないため、ほとんど海外から輸入されています。体をつくるもとになるタンパク質が多く含まれていますが、肥るもとになる脂肪が少なく、血液をサラサラにしたりする健康に良い成分がたくさん含まれています。えびのカラを食べない人が多いですがカラには血液をサラサラにしたりお腹のクリーニングをする成分もあるので食べられる人は食べるようにしましょう。
【給食献立】 2022-02-07 17:04 up!
2月4日
ご飯 牛乳 鶏肉のペキンダック風 白菜の甘酢和え 卵スープ
今日から中国でオリンピック、パラリンピックが始まりました。そこで給食でも中国の北京料理として有名な北京ダックをアレンジした北京ダック風を作りました。
北京ダックはアヒルを焼いてから皮をそいで小麦粉で薄く作った皮にきゅうりや長葱と一緒に包んで食べます。500年前頃は中国の身分の高い人だけが食べていた料理ですが、だんだんと普通の人たちも食べられるようになり、今では世界の色々な国で食べられるようになりました。また、もう一つ白菜の甘酢和えは中国語でラーパーツアイと言って冬野菜の白菜を使った甘くて辛い和え物で四川省の代表的な料理です。
【給食献立】 2022-02-06 19:51 up!
1年生の様子
本日の様子です。生活科「風となかよし」では、紙コップで作った風車を回るかどうか試す学習をしました。曇り空でしたが元気よく走って、風車を回していました。少し風が吹いていたので、止まっていてもクルクルと回っていました。
【1年生】 2022-02-06 19:50 up!
5年生の様子
本日の5年生の体育の様子です。跳び箱で開脚跳びの練習をしました。開脚とびでは、手の付き方、着地の仕方、体の使い方を意識しながら跳んでいました。
【5年生】 2022-02-06 19:50 up!
3年生の様子
3年生の道徳の様子です。アンパンマンの作者・やなせたかしさんがどんな思いでアンパンマンを生み出したのかについて学び、自分だったらどんなことをして人を喜ばせたいかを考えて発表しました。
【3年生】 2022-02-06 19:50 up!
5年生の様子
5年生の様子です。算数の「整数と小数」、「小数の割り算」の単元の確かめテストを行いました。
【5年生】 2022-02-06 19:50 up!
6年生の様子
6年生の様子です。卒業文集にとりかかっています。将来の自分の姿やそのためにどんな努力が必要なのかについて、考えながら取り組んでいました。
【6年生】 2022-02-06 19:49 up!
2月3日
節分ご飯 100%オレンジジュース 鰯の蒲焼き 吉野汁
今日2月3日は節分です。節分は立春の前の日に当たる日です。まだまだとても寒いですが暦の上では明日から春になります。節分には豆まきをします。
豆まきには大豆を使いますが、昔は大豆ではなくお米をまいていました。大豆は昔から魔物を滅ぼす特別な力があると信じられてきました。豆をまくと災難や病気を寄せ付けないと言われ、人々が健康に過ごせるように願って豆をまきます。また節分の日には鰯の頭を焼いてヒイラギの小枝に刺します。鰯は臭いが強いため鬼を寄せ付けないからです。またヒイラギが鬼の目を刺すとも言われています。今日は給食でも大豆を使った節分ご飯、そして鰯の蒲焼きを作りました。しっかり食べて1年間健康に過ごしましょう。
【給食献立】 2022-02-06 19:49 up!
 Chromebookで発生した事象の報告及び対応について
Chromebookで発生した事象の報告及び対応について
【お知らせ】 2022-02-04 17:23 up!
2月2日
ハニートースト 牛乳 ハンガリアンシチュー ジュリエンヌサラダ
今日のシチューのハンガリアンシチューは別の名前をグヤーシュと呼びます。ヨーロッパにあるハンガリーという国の家庭で最もよく作られるシチューとして有名です。本来は牛肉を使いますが、給食では豚肉を使っています。たまねぎ、トマト、じゃがいも等をじっくり煮てパプリカパウダーを使うことが特徴です。ハンガリーで牛を飼っている人たちが大きな鍋でこのスープを作るようになり牛を飼う人をグヤーシュと呼ぶことから、この料理名がついたそうです。ハンガリーだけでなくヨーロッパにあるドイツやオーストリア、チェコ、ポーランドまたアジアにあるモンゴルではグリヤシと呼ばれており、色々な国で作られています。
【給食献立】 2022-02-02 18:34 up!
2年生の様子
2年生の算数の様子です。図を用いて式を考える学習をしていました。問題の文章をテープ図を使って考え、全部と部分を求めるときの式の違いに気付くことができていました。
【2年生】 2022-02-02 18:33 up!
2月1日
豚肉のおろし丼 牛乳 野菜のごま酢和え りんご
大根は1年中出回っていますが本来は冬の野菜です。
大根にはビタミンCやアミラーゼ、ポロテアーゼ、リパーゼという3つの酵素が含まれていて、この酵素は腸内環境を整えたり、消化不良や便秘などの不調を整えます。また大根の辛い成分はイソシアネートと言われているものでガンを防いだり、血液をサラサラにする働きもあり健康によい成分がたくさんあります。
【給食献立】 2022-02-02 18:33 up!
季節の俳句
板二小が環境学習の一環として取り組んでいる「季節の俳句」の冬の俳句が廊下に飾られています。冬の自然に注目した作品が並んでいます。
【環境】 2022-02-02 18:33 up!
2年生の様子
2年生の国語の様子です。「かさこじぞう」の単元で、場面の様子やじさまの気持ちを読み取る学習をしました。おじぞうさまがたくさんごちそうを運んできてくれる場面を一言一句意味を確認しながら読むことができました。
【2年生】 2022-02-02 18:33 up!
1年生の様子
1年生の国語の様子です。新出漢字を練習していました。先生のしてくれる字形の説明をしっかりと聞きながら、一文字一文字丁寧に書いていました。
【1年生】 2022-02-02 18:32 up!
児童朝会
本日の児童朝会の様子です。校長先生からは、地域の方から板二小の児童が倒れた自転車を直すことを手伝ってくれたとの感謝の電話があったとの紹介がありました。困った人を助けられる人は、大人子供関係なく立派です。
後半は、書き初め展の表彰がありました。6年生が代表して、賞状を校長先生から受け取りました。
【できごと】 2022-02-02 18:32 up!
1月31日
ご飯 牛乳 茎わかめの佃煮 鰤の照り焼き 沢煮碗
鰤は体の長さが1m、体重は8kgで、せなかが暗い青色、おなかは銀色で、体に黄色の線がある魚です。地域によって呼び名がかわり、ワカシ、イナダ、ワラサ、フクラギ、イナダ、ハマチなどと呼ばれています。鰤という漢字は魚に師と書きますが師走(12月)の時期が一番おいしいので鰤と呼ぶようになったといわれています。鰤を養殖したものをハマチと呼びますが最近はハマチの量が倍以上となっています。
鰤が一番おいしいのは卵を産む前の脂がのる冬です。この時期の鰤は寒鰤とよばれ脂肪が多く独特の風味があります。全国で天然の鰤のとれる県は
1位、長崎県、2位、島根県、3位、千葉県となっています。今日、給食で使っている鰤は東北の三陸の海でとれたものです。
鰤の脂肪は血液をサラサラにしたり、脳の働きをよくする働きがあります。このほかにも高血圧予防、貧血予防、老化予防、骨粗しょう症予防などを含む健康に良い栄養素がたくさんあります。
【給食献立】 2022-02-02 18:32 up!